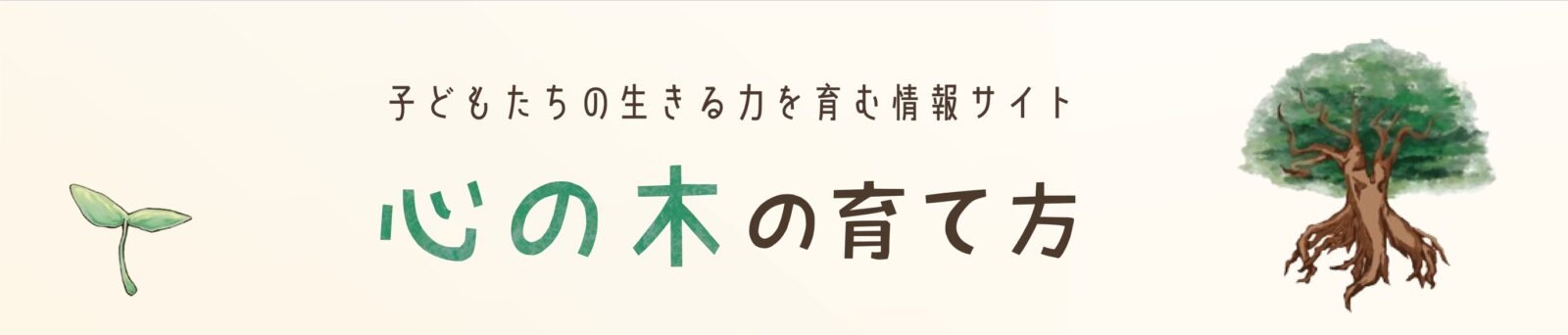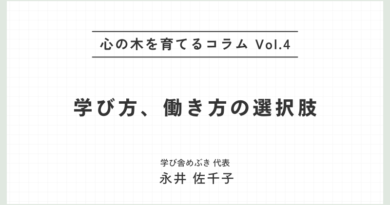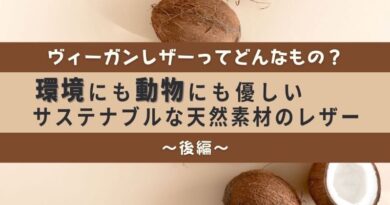発がん性にも影響?避けたい添加物とは〜食品添加物の基礎知識②
食品添加物は私たちの食を便利にしてくれる一方で、体への影響も心配されます。忙しい生活を送る中で加工食品やインスタント食品全てを避ける事は難しいこともありますが、体にどのような影響を与えるかを知っておくことは大切です。そこで、前回に続き今回は特に体への影響が心配される添加物についてご紹介します。
前回記事
Contents
1.合成着色料(タール色素)
着色料は食品の製造、加工時に色をつける目的で使用され、合成着色料と天然着色料があります。日本で使用が認められているタール色素は12種類ですが、海外ではその多くが禁止されており、体への影響が心配されます。日本でも、過去に発がん性などの毒性が認められ使用禁止になった物が数多くあります。
使用例
菓子類、漬け物、畜産物加工品、魚介加工品など
着色料の種類
天然着色料(コチニール色素、パプリカ色素など)
動物や植物、鉱物などの自然界に存在する天然色素を人工的に取りだしたもの
合成着色料(タール色素)
主に石油精製の際に得られるナフサを原料とした化成品から生産される
(赤色2号、黄色4号など番号が振られている)
日本で認められている合成着色料は12種類・・・しかし、海外では使用を禁止しているものも!
食用赤色2号
用途:菓子類、アイスキャンデーの着色など
発がん性があるとして、アメリカ、韓国などで使用禁止
食用赤色3号
用途:かまぼこ、漬物の着色など
発がん性、染色体異常のリスクから、アメリカ、ドイツ、ポーランドなどで使用が禁止
食用赤色40号
用途:清涼飲料水、菓子類の着色など
イギリスでは注意欠陥・多動性障害(ADHD)と関連が疑われるとしてメーカーへ自主規制を促した
食用赤色102号
用途:漬物、菓子類の着色など
アメリカ、カナダ、ベルギーでは食品への使用が禁止されている
食用赤色104号
用途:ソーセージ、菓子類の着色など
遺伝子損傷などを生じるとして国によっては禁止されている
食用赤色105号
用途:ソーセージ,菓子類の着色など
食用赤色106号
用途:ハム、ソーセージなどの着色など
食品添加物として使用されるのは日本だけ
食用黄色4号
用途:ゼリー、シロップの着色など
イギリスでは注意欠陥・多動性障害(ADHD)と関連が疑われるとしてメーカーへ自主規制を促した
食用黄色5号
用途:清涼飲料水、菓子類の着色など
食用緑色3号
用途:清涼飲料水、菓子類の着色など
食用青色1号
用途:清涼飲料水、菓子類の着色など
ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン、オーストリアでは使用を禁止している
食用青色2号
用途:チョコレート、和菓子の着色など
発がん性の問題で国によっては使用禁止にされている
出典:食用色素の化学
過去に日本で使用禁止になった着色料
発がん性などの危険性から、使用禁止になった着色料
ADHDとの関連性も指摘されている
英国食品基準庁 (FSA)は2008年4月、注意欠陥・多動性障害(ADHD)と関連の疑われる合成着色料6種類について、食品メーカー等に自主規制を促しました。
出典:内閣府食品安全委員会
合成着色料を使ったお菓子やジュースはパッと目を惹き綺麗ですが、体にとって安全とは言えません。着色料を使わなくても、赤色はビーツやラズベリー、黄色はマンゴー、人参で、紫キャベツを使えば青色を作ることもできます!素材本来の色でお料理やお菓子作りを楽しみたいですね♪
色付けにおすすめの商品
ビーツパウダー
かぼちゃパウダー
小松菜パウダー
2.合成甘味料(アステルパーム・スクラロース・エリトリトール)

甘味料は、食品に甘みを与える食品添加物で、天然甘味料と人合成甘味料に分類されます。合成甘味料は、「ゼロカロリー」や「カロリーオフ」など、健康を意識した商品の甘味料として人気が出た一方で、強烈な甘さに慣れ、砂糖を過剰に摂取してしまうなどの心配もあります。
また、「アスパルテーム」は2023年7月、世界保健機関(WHO)傘下の国際がん研究機関(IARC)により「ヒトに対する発がん性を持つ可能性」のリストに掲載されることが決定しました。
疲れたときに甘い物が食べたくなったり、甘い物と食べるとホッとするという方も多いと思いますが、「砂糖はダメ」と一切を絶つのではなく、量や質にこだわって選んでみましょう。
使用例
菓子類、清涼飲料水、ガムなどに甘味をつける為に使用されます。
甘味料の種類
天然甘味料
植物や果実に含まれている甘み成分を取り出し精製、濃縮したもの
(サトウキビ、メープル、ハチミツなど)
合成甘味料
食品に存在しない甘み成分を人工的に合成したもの(アステルパーム、サッカリン、スクラロースなど)
合成甘味料の甘さは砂糖の600倍!?
合成甘味料の甘味度は、砂糖に比べアステルパーム200倍、スクラロース600倍と言われています。少量で甘味がつけられることからダイエット食品、お菓子、清涼飲料水などに広く用いられていますが、一方で、合成甘味料は糖尿病のリスクを上げることが報告されています。
また、砂糖に比べ、200~600倍という強烈な甘みを持つ人工甘味料に舌が慣れてしまうと、甘味に対する味覚が鈍ってしまい、果物などの自然の甘さでは物足りなくなり、ついついお菓子などの甘い物を食べすぎてしまいます。
体に優しい甘味料
ドライフルーツ
自然で優しい甘味が楽しめます。

ご購入はこちら→ 信州産シャインマスカット、巨峰、ミックスのドライフルーツ
羅漢果
本みりんのアルコールを飛ばし、旨味と甘味だけを残した低GI甘味料。
3.防カビ剤(OPP、TBZ、IMZなど)

海外から輸入されるオレンジやレモンなどの柑橘類、バナナなどの果物類は、輸送、貯蔵中にカビが発生することがあり、それを防止するために防かび剤が使用されます。食品衛生法では、農薬ではなく食品添加物として使用が認められています。
使用例
輸入果物(主に柑橘類やバナナなどの果物類)の防かび剤
IMZ(イマザリル)
イマザリルは防かび剤として使用されますが、日本では、その毒性から農薬としても使用が認められていません。
リスク:生殖器、胎児への影響、肝臓の障害
OPP(オルトフェニルフェノール)
1955年に農薬として登録されたが、1969年に失効。その後、1977年に食品添加物としての認可を受けた。
リスク:ラットによる実験で、腎臓と膀胱にガンが認められる
TBZ(チアベンダゾール)
1972年に農薬として登録され、1978年に食品添加物としての認可を受けた。
リスク:肝臓(肝細胞 肥大等)、甲状腺(ろ胞細胞過形成等)、腎臓(腎盂移行上皮過形成等)及び血液 (貧血等)への影響、ウサギによる発生毒性試験では胎児に奇形の発生頻度増加が認められた。
出典:内閣府 食品安全委員会
表示をチェックしよう!
防カビ剤を使用した柑橘類やバナナなどの果物を販売する場合、バラ売りであっても、値札や陳列棚に使用した物質名を表示するように決められています。
防カビ剤は水洗いしただけではほとんど落ちないため、ジャムやドリンク、お菓子などに果皮ごと使用する場合、十分気をつける必要があります。日本では収穫後の防カビ剤の使用は禁止されていることから、国内で栽培された果物を使うのが好ましいでしょう。
子どものおやつを買う前に、是非食品表示をチェックしてみましょう。
編集部おすすめのおやつ
学び舎めぶき発、完全植物性ジェラート「SOBOKU」は、その名の通り、シンプルさにこだわった商品です。
乳製品を使用していないため、乳アレルギーの方も安心してお召し上がりいただけます。
白砂糖も不使用のため、優しい甘さが口の中に広がる逸品です。
あなたの応援が、若者の未来につながります
「SOBOKU」は、長野市で若者の就労支援を行っている学び舎めぶきのプロジェクトです。
社会に出られず悩む若者が、ジェラート事業を通じて、少しずつ働く力を身につけています。
皆さまの応援をどうぞよろしくお願いいたします!
こちらからご購入いただけます!!

心の木の育て方オンラインショップでは、からだに、地球に優しい商品を販売しています
『心の木の育て方オンラインショップ』は、地球や動物に優しい製品を求める方、家族の健康を願う方、妊娠中や子育て中の方が心おきなく買い物を楽しめるショップです。農薬不使用のたかきび、自社農場で育てた農薬不使用のライ麦粉、産直無添加のりんごチップス、卵もバターも使わないふんわり米粉パンやハンバーグ、スイーツ、蜜蝋不使用のエコラップ、赤ちゃんや妊婦さんに優しいお洋服、木の温もりを感じるキッズチェアなどなど、厳選し、心をこめて販売しているラインナップとなります。ぜひ一度覗いてみてください♪

心の木の育て方のSNS
世界マザーサロンでは、X(旧Twitter)、Instagramにて情報発信しております。
各活動の最新情報もこちらからご確認いただけます。
ぜひ、ご登録ください!
X(旧Twitter)
https://twitter.com/vegan_kosodate
https://www.instagram.com/wmsalon.nagaisachiko
心の木の育て方のメルマガ
心の木の育て方サイトは、一般社団法人世界マザーサロンのプロジェクトです。
メルマガでは、代表の永井佐千子のメッセージと共に活動の最新情報等をお送りしています。
これからの子育てや生き方について、一緒に考えてみませんか?
是非この機会にご登録ください!ご登録はこちらから

永井佐千子(Sachiko Nagai)
<経歴> 大学卒業後、北京に語学留学 2002年より経営コンサルティング会社で日系企業の中国事業支援に従事
その後、上海の法律事務所で勤務後、2008年に独立 母親が在宅で仕事ができる環境を整えながら企業の事業支援を行う
2015年 一般社団法人世界マザーサロンを設立 2021年 学び舎めぶきを開所 子どもたちの未来を守りたい!!
という強い想いのもと、現在、国内外の仲間と共に活動を進めている。
一男一女の母
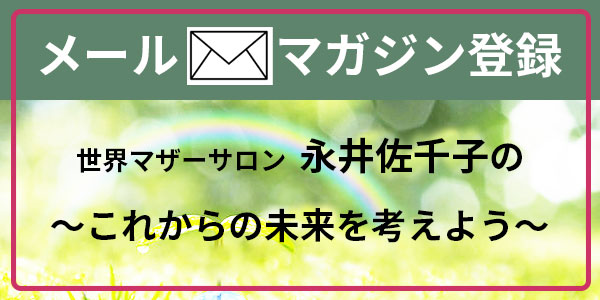

『心の木の育て方』についてのご質問はこちらからお願いいたします。

※現在、日本では「VEGAN」を「ヴィ―ガン」「ビーガン」の2通りで表記されていますが、意味は同じです。当サイトでは「ヴィ―ガン」で統一しています。